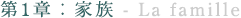
Prev
Next
-
フランス革命による社会的構造の抜本的な変革と、その後のナポレオン法典の整備などは、市民的な家族、家庭の創出に貢献しました。革命以前の絵の中の子ども、家族の大半は貴族や富裕層の注文によるもので、彼らの下にあった「第三階級」(市民階級)が描かれることは稀でした。革命後の共和主義的かつ市民的な社会にあっては、家族・家庭は社会の「核」、「細胞」的な存在となり、子どもの存在意義もまたかつてないほど高まったことは、出品作品からも見てとれるでしょう。今回出展されるデュビュッフの作品は、画家自身の家族ひとりひとりの肖像であると同時に、家族の絆を主題としている点でも注目されます。同じことはアルマ=タデマ、アルディッティについてもいえます。また、画風は異なるものの、ギヨーム・デュビュッフ、カリエール(no.4)、ロールなどは、貴族から庶民の子どもまで、かつてないほど幅広い社会層の子どもたちが描かれるようになったことを物語っています。
no.3 パブロ・ピカソ 《パロマ》no.4 ウジェーヌ・カリエール《病気の子ども》
-
クロード=マリー・デュビュッフは、《ナポレオンの戴冠式>で知られる新古典主義の巨匠ダヴィッドの弟子。父からの金銭的援助のなかったデュビュッフは授業料をアルバイトで、つまりオーケストラでヴァイオリンを弾くことでひねり出した。初めはダヴィッド風の歴史画、神話画を描いていたが、1830年代の7月王政の時代には肖像画家としての人気と地位を確立した。
この絵は《デュビュッフ一家。1820年》と銘打たれており、この年が彼、あるいは家族にとって特別な年であったことをうかがわせる。単に画家が30歳になった区切りとして、ということも考えられるが、この年彼は妻をモデルとした肖像で成功しているので、肖像画家としてのデビューを記念して描かれたとも考えられる。画面には7人の人物が描かれているが、画面右手のカップルが画家夫妻、中央のあどけない子どもは、生まれてまもないエドワールである。画面左からさす光と、ダヴィッドゆずりの正確、克明なデッサンにより、また背景が暗い無地であることにより、それぞれの人物がくっきりと浮かび上がっている。家族の肖像ではあるが、人物の視線や顔の向きはバラバラで統一感に欠ける。しかしこれは17世紀のオランダの群像形式の肖像画以来の伝統で、むしろ単調で機械的なポーズ、構図を嫌ってのことかと思われる。
-
カリエールは印象派世代の画家であるが、印象派との直接的なつながりは薄く、むしろ象徴派に近い。といって神話的、文学的主題を好んで手がけたモロー、ルドンなどの象徴主義者とも一線を画している。彼の最大のトレードマークは「カリエールの霧」と呼ばれたデリケートな灰色、褐色でおおわれたほとんどモノクロームの、時に神秘的とも思える画面である。人や物が文字通り霧の中から浮かびあがるような、その曖昧模糊とした画風は「朦朧体」というにふさわしい。
家族を人類という共同体の細胞、ミクロコスモス(小宇宙)と見るカリエールにとって、家族は常に重要なテーマであった。1885年のサロンに出品されたこの作品は、サイズ的にもカリエール最大級の作品である。元気に走りまわる子どもではなく、病める子と、これを気遣う母親というのもカリエールらしいが、他にも2人の子ども、どこか心配そうなペットの犬、テーブルの上の皿やポットなど、カリエールとしては比較的克明に描いているのは、サロンに出品することを考慮してのことであろう。