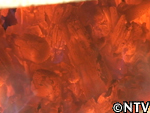| 材探し 村の里山で白炭の材料探し。黒炭の時にも使用した堅い材質のコナラの木を探し、伐採する。炭木に適するのは樹齢15〜20年の幼木。白炭で焼くには直径15cm以内であれば一本木として活用でき、より良質な炭となる。水分含量の多い夏場の伐採後は、程よく木を乾燥させてから炭木として活用する。葉の枯れ具合が乾燥の目安になる。 |
   |
| 口焚き 原木の水分をとばし乾燥させると共に窯の温度を炭化点である320℃〜350℃まで上げ、自然着火させる作業。約2時間かかる。焚き口にて木を燃やし続ける。出る煙は水蒸気状の水煙(みずけむり)。 |
   |
| 窯出し 窯内の温度が1000℃を超えると、中の炭が黄金色を帯びてくる。これが窯出しの合図。黄金色を帯びたものからどんどんかき出し、灰と山砂に水分を足した消灰(スバイ)をかけ鎮火させることで、さらに炭を締まらせる効果がある。 |
         |
| 立て股 白炭づくりの特徴は、1回で終わるのではなく炭焼きを連続して行うことである。窯がまだ熱を帯びた状態なので、2回、3回と繰り返す事で、最高温度が1200℃を超えより締まった炭ができるという効果がある。また熱を帯びた状態なので口焚きをしなくても自然に原木が乾燥し着火するというメリットもある。中の原木に炎があがってしまった場合は消しながら、一気に原木を詰め込まなければならない。 |
      |
| 完成 |
         |