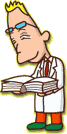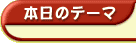
|
江戸に学ぶ生活の科学
#576 (2001/04/08)
|

|

久々登場の科学の素浪人、矢野左衛門。実は矢野左衛門は、江戸時代からタイムスリップしてきたのでした。いったい矢野左衛門の過ごしていた江戸時代の生活はどんなものだったのでしょう?調べてみると、江戸時代の生活にもいろいろ科学の知恵があったのです。
朝起きてまずする事といえば歯磨き。なんと、江戸時代にも既に歯磨きの習慣はあったのです。ヤナギやクロモジ等の木を細く削り、煮て柔らかくした先端を木槌で叩いてブラシ状にした、その名も房楊枝。江戸時代にはこれを毎日使い捨てにすることが粋だったようです。
 さらに、江戸時代には、ちゃんと歯磨き粉もあったのです。歯磨き粉には、房州砂という、砂の上澄みを乾燥させた細かい砂に、丁子、じゃ香、ハッカ等の香料を混ぜたものが使われていました。現在の練り歯磨きと比べてみるために、両者でアクリル板をこすると、江戸時代の歯磨き粉の方にたくさんの傷がつきました。電子顕微鏡でのぞくと、なるほど江戸時代の歯磨き粉は、現代の練り歯磨きよりも粒子がゴツゴツしていました。これはもしかすると、江戸時代の歯磨き粉の方が現代のものよりも良く磨けるのか!?ということで、矢野左衛門の仲間達と歯磨き実験です。それぞれの歯磨き粉で、左右の歯を磨き分けてもらいました。すると結果は何と、どちらも汚れの落ち方に差はありませんでした。しかし房楊枝には意外な弱点が・・・。房楊枝はその形状のため、歯の裏が磨けなかったのでした。
さらに、江戸時代には、ちゃんと歯磨き粉もあったのです。歯磨き粉には、房州砂という、砂の上澄みを乾燥させた細かい砂に、丁子、じゃ香、ハッカ等の香料を混ぜたものが使われていました。現在の練り歯磨きと比べてみるために、両者でアクリル板をこすると、江戸時代の歯磨き粉の方にたくさんの傷がつきました。電子顕微鏡でのぞくと、なるほど江戸時代の歯磨き粉は、現代の練り歯磨きよりも粒子がゴツゴツしていました。これはもしかすると、江戸時代の歯磨き粉の方が現代のものよりも良く磨けるのか!?ということで、矢野左衛門の仲間達と歯磨き実験です。それぞれの歯磨き粉で、左右の歯を磨き分けてもらいました。すると結果は何と、どちらも汚れの落ち方に差はありませんでした。しかし房楊枝には意外な弱点が・・・。房楊枝はその形状のため、歯の裏が磨けなかったのでした。
朝ご飯を食べるのには、やはり火をおこさなくてはなりません。江戸時代には、ご存知火打ち石がありました。さっそく火をおこそうとする矢野左衛門。しかし火打ち石といったものの、実際矢野左衛門が持っているものは、石と鉄だったのです。実は火をつけるには、石英質の硬い火打ち石と鉄で出来た火打ち金の2種類が必要なのです。この2つを強い力でぶつけ合うことにより、火花が飛ぶのです。火花の散った所を顕微鏡で観察すると、石の破片や削れた鉄に混じって溶けて玉になった鉄が見えました。何とこの鉄の玉こそが、火花の正体です。火打ち石を打った瞬間、石と鉄のかけらが飛び散り、鉄の方が溶けて高温の火花となるのです。けれど、燃えやすい紙に火をつけようとしても、全く火がつく様子はありません。どうしたらこの火花で火がつくのでしょうか?
 そこで登場するのが「ホクチ(火口)」です。ホクチとは、ガマの穂を不完全燃焼させて炭化させたものです。このホクチの上で火打ち石を打つと、小さいながらも確かに火はつきました。なぜホクチにはひがつくのでしょう?ホクチは紙などよりも繊維が細かくほぐれた状態で、細かい方が表面積は広く、酸素と触れている場所も多いので、火が強いのです。更に炭化したことにも秘密はありました。生のガマの穂が炎を上げるものの、あっという間に燃え尽きたのは、植物に含まれた揮発性のガスが燃えていたからで、炭素だけがゆっくり燃える炭は、とても火持ちがいいのです。このホクチの小さな火を大きくするのが「付木」です。木の端にイオウをつけた付木を近づけると、見事に火がつくという訳です。
そこで登場するのが「ホクチ(火口)」です。ホクチとは、ガマの穂を不完全燃焼させて炭化させたものです。このホクチの上で火打ち石を打つと、小さいながらも確かに火はつきました。なぜホクチにはひがつくのでしょう?ホクチは紙などよりも繊維が細かくほぐれた状態で、細かい方が表面積は広く、酸素と触れている場所も多いので、火が強いのです。更に炭化したことにも秘密はありました。生のガマの穂が炎を上げるものの、あっという間に燃え尽きたのは、植物に含まれた揮発性のガスが燃えていたからで、炭素だけがゆっくり燃える炭は、とても火持ちがいいのです。このホクチの小さな火を大きくするのが「付木」です。木の端にイオウをつけた付木を近づけると、見事に火がつくという訳です。
江戸時代の洗濯はいったいどのようなものだったのでしょう? 実は洗剤には、米ぬかや米のとぎ汁、そして灰汁が使われていたのです。いったいなぜ、米ぬかで汚れが落ちるのでしょう?米ぬかの成分を調べてみると、驚きの結果が。なんと油分が20%近くも含まれているのです。実際米ぬかから作ったサラダオイルもあるほどです。けれど米ぬかに水を入れても、水は白く濁るばかりで、油分はちっとも浮いてきません。実はこれは乳化と呼ばれる現象です。乳化とは、普段混ざらない水と油が、界面活性剤となる洗剤を入れることで混ざり合って白くなる現象です。米ぬかに含まれる「γグロブリン」というタンパク質が界面活性剤の役割を果たしているというのです。そこで現代の洗剤と比較実験です。オイスターソースのしみをTシャツにつけ、それを手洗い、米ぬか、現代の洗剤で洗い比べて見ました。すると驚くことに、米ぬかは手洗いを上回ったのはもちろん、現代の洗剤にも勝るとも劣らない洗浄力を見せたのです。恐るべし、米ぬか!
はたして江戸時代、時計もほとんど無かったこの時代、時間はどのようにして知られていたのでしょうか?夜も大した照明のなかった江戸時代の人々の生活は、いつも太陽とともにありました。太陽が昇る直前を明け六ツ、日が暮れた直後を暮れ六ツと呼び、その間を昼と夜それぞれ六等分して一刻(いっとき)という時間の長さを決めていたのです。しかしこの時間、季節によって、日の出、日の入りの時刻は変化するため、一刻の長さも季節によって変わりました。太陽の出ている時間が最も短い冬至の昼の一刻が1時間50分なのに対し、夏至の昼の一刻は2時間40分と、なんと50分もの差がありました。つまり気候のいい夏は昼の時間が長く、寒い冬は働く時間が短くなり、つまり江戸時代にはサマータイムがあったのです。このように江戸時代の時間は、一定の幅でない「不定時法」と呼ばれるものだったのです。ちなみに、“おやつ”や“正午”といった言葉は、こうした江戸時代の時間のなごりだったのです。現代の昼12時に当たるのが、昼の九ツ、そこから一刻たった時間が昼の八ツ。この時間に間食をとる習慣が現代に残っているというわけです。また、時間を十二支で表す言い方もあり、昼の九ツは「午の刻」。といって午の正刻ということで、お昼ちょうどを「正午」と呼ぶのです。そして、午の刻の前を午前、後を午後というのも、このなごりなのです。

|
江戸時代の時刻は太陽とともに長くなったり短くなったりした!
|
|
|
|
|
|